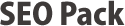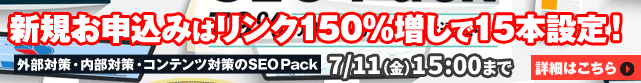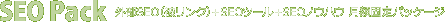SEO対策はSEOツール(内部対策+コンテンツ対策)+外部対策で月額7,980円
Content is King
コンテンツイズキング
この記事では、コンテンツイズキングとは何か、コンテンツイズキングの考え方を理解し、順位を上げるための実際のSEO対策手順を紹介します。
コンテンツイズキングとは?
昨今、サイト運営では、『コンテンツイズキング』を重視する風潮が高まっています。『コンテンツイズキング』とは、「サイトにとってコンテンツが最も重要である」という考え方のことで、具体的にはサイト内のコンテンツの質を上げることによって、Googleからの評価を上げることを目指します。
SEO対策を行う人なら一度は目にする「コンテンツ・イズ・キング」というフレーズ。これはただのバズワード(流行り言葉)ではなく、実はSEO対策の本質を表した言葉で、サイト順位上昇と絶対に切り離せない考え方です。
『コンテンツイズキング』が唱えられるようになった背景には、被リンク対策に対するGoogleの取り締まりが厳しくなっていることがあります。
かつて被リンク対策では、低品質な被リンクでも数を貼れば高いSEO効果を発揮していましたが、Googleアルゴリズムが日に日に改善され、現在では低品質な被リンクを貼ってもSEO効果を期待することができなくなりました。
こうした状況を受けて、今後も一層取り締まられる被リンクよりも、Googleの推奨している質の良いコンテンツを重視したほうが良いだろうと考えられるようになったのです。
Googleが目指す「ユーザー視点」
Googleは「コンテンツの質が良いサイト」を上位表示させるように取り組んできました。それは、ユーザーにとって役に立つサイトを上位表示することを目標にしているからです。SEOにおいて、その重要さを表したフレーズとして知られるのが、この「コンテンツ・イズ・キング」です。
Googleが被リンク対策を取り締まっているのも、ユーザーにとって役に立たない「コンテンツの質が悪いサイト」が上位に蔓延らないようにするためです。では、Googleがどのような基準で「コンテンツの質」を判断しているのかというと、以下の3つの基準があるとされています。
- 記事の内容がオリジナルであるかどうか
- サイトの内容と記事の内容がマッチしているかどうか
- 記事が定期的に投稿されているかどうか
これら3つの基準も勿論、ユーザー視点に立って作られています。ウェブマスターがGoogleに認められるような質の高いコンテンツを作ろうと思ったなら、それはユーザーに認められるコンテンツを作るということなのです。
\無料診断の活用で課題を明確に/
外部リンク、内部状況、コンテンツ状況からSEO対策の課題が見えてくる無料調査です。
「対策ページの弱点は何か...」などお悩みをお持ちの方は、一度「SEOパーソナル診断」をご利用ください。
コンテンツイズキング のSEO対策手順
コンテンツイズキングの考え方に基づいたコンテンツを作るにはどうすればよいのでしょうか? 次は、「コンテンツイズキング」のフレーズにふさわしい高品質なコンテンツを作ってSEO対策の土台を作る手順を紹介します。
コンテンツイズキング対策手順(1) コンテンツの全体像をイメージする
あなたのページを「高品質なコンテンツ」にするために、まずはコンテンツのイメージを思い浮かべ、下記の条件を満たしているか自問自答してみてください。
- そのコンテンツは読者の役に立ちますか?
- 読者から見て、他にはないユニークなコンテンツですか?
- 数秒以上読み進めても苦ではないコンテンツになっていますか?
全てOKのコンテンツがイメージできたら、次はキーワードを決めましょう。
コンテンツイズキング対策手順(2) キーワードを決める
次は、あなたのコンテンツに関連してユーザーが検索しやすい「キーワードを調査」します。
いくらよくできたコンテンツでも、ユーザーが訪問してくれなければコンテンツを作成した意味がないからです。
キーワードを選ぶ際に、例えば、同じ意味で使われることの多い「ばんそうこう」と「バンドエイド」という言葉があります。ページにより多く集客するには、どちらか検索数がより多いワードを選ぶ必要がありますが、このような時には、SEOツールを利用すると便利です。

上の画像は、SEOツール「seodoor」のキーワードデータベースという機能で調査した結果です。「バンドエイド」の方が、圧倒的に月間予測検索数がある事がわかります。
キーワードの検索数調査では、無料の キーワード難易度チェックツールが使えます。
また、SEOエキスパートからの助言を受けたいSEOビギナーの方などは、SEOキーワード無料相談窓口を利用すると簡単なキーワード調査や対策のヒントが得られます。
コンテンツ内容として売りたいものや見せたい情報さえあらかじめ決まっていれば、このいずれかの方法で最適なキーワードが決められます。
コンテンツイズキング対策手順(3) コンテンツを作る
多くの人が検索しそうなキーワードが見つかったら、そのキーワードに応じてコンテンツを作る、もしくは既存ページを編集します。
新規コンテンツを作るなら、キーワードを意識してコンテンツを書きます。あるいは、既にコンテンツがあるなら、キーワードを入れ込みます。ページ内のキーワード使用回数や使用率に基準値のようなものはなく、あくまで「自然に」キーワードを入れるようにしてください。
また、コンテンツ作成時には、手順(1)で自問したポイント、つまり「読者の役に立つか」「読者にとってユニークか」「読者が苦労せず読み進められるか」を強く意識しましょう。
コンテンツイズキング対策手順(4) フレッシュなコンテンツも意識する
コンテンツ作成の手法の一つとして、特にブログなどでは、フレッシュな話題を織り込むことで、時に大きな集客効果を得られることがあります。Googleはその時々のフレッシュな話題に関連したコンテンツの順位を大きく上げることがあるためです。
なお、このGoogleの機能はQDFと呼ばれます。
このため、ブログ記事などを書く際に常にフレッシュな話題に気を配っておき、タイミングを見てそれを盛り込んだ記事などを書くと、QDF効果に乗った際には、集客を大きく増加させることができます。
とはいえ、話題がフレッシュでなくなるとQDF効果でついた順位もすぐ落ちる(元に戻る)ため、QDF狙いはあくまでオプションとして考えるのがよいかもしれません。
対策の成果を必ずチェックしよう
ここまで、具体的な対策手順を紹介してきました。
「コンテンツイズキング」の考え方によるSEO対策とは、つまり「高品質なコンテンツ作成」にほかならない、ということが理解できたのではないか、と思います。
ただ、完成したコンテンツをアップロードしただけで満足せずに、成果確認を行うということを忘れてはいけません。
対策の成果チェック方法
コンテンツを含めた基本的な対策が済んだら、次の二点を確認します。特に、集客の軸になるコンテンツ(ページ)については、必ず確認するようにしましょう。
- 検索順位
- ユーザー訪問数
力を入れたコンテンツは、通常一日ごとに順位や訪問数を確認します。その確認の中で、コンテンツ改善したのに順位が上がっていない、といった場合は、再度コンテンツを見直す事が大切です。
コンテンツ改善だけで終わらせない
いくら高品質なコンテンツを作っても、もう一つの最重要要件である被リンク対策を済ませていないと順位が上がらないのは、Googleの発言のとおりです。特に注力するページでは、コンテンツ品質対策と被リンク対策を、必ず両方同時に行って下さい。
その他のSEO対策、例えば、細かい内部SEO調整などは、上記の2つの基礎SEOで成果が出た後に、追加施策として行うことをおすすめします。こうすると、効果的に対策の成果が出ます。
参考:ビル・ゲイツの初出原稿全訳+α
実は、この「コンテンツ・イズ・キング」というフレーズの初出は、1996年のビル・ゲイツによるMicrosoftサイト掲載エッセイ "Content is King"(英語)だと言われています。本記事執筆にあたり筆者が原文をすべて日本語訳出したものを、参考資料としてこちらに掲載します。
まだSEOどころかGoogleも存在しなかった1996年、すでに現在のコンテンツベースSEOを含むオンライン・マーケティングを予見していた、「すごすぎるエッセイ」としても知られる文章です。一読すれば、誰しもビル・ゲイツの慧眼に驚くことでしょう。
※原文は平打ちで少々読みづらいため、筆者判断で見出しやイメージを入れてあります。読みやすくなったかとは思いますが、原文の雰囲気で読みたい場合は、適宜読み飛ばして下さい。
コンテンツ・イズ・キング:コンテンツこそが王である
ビル・ゲイツ, 1996年3月1日オンラインで金銭を生むのは「コンテンツ」である
私が思うに、インターネットで金銭を生み出すもの、それは、コンテンツだ。 かつて、テレビやラジオでコンテンツが金銭を生んでいたのと、同じように。 半世紀前に起こったテレビ革命は、テレビ製造会社など、数多くの産業を生み出した。しかし長期的に見ると、そこで最も成功を収めたのはやはり、テレビというメディアを使って情報や娯楽を提供した者たちだ。どんな企業でも「コンテンツ」を持っている
インターネットのような、作り手と受け手が互いに情報をやりとりするネットワーク(=インタラクティブネットワーク)では、「コンテンツ」という言葉の意味はきわめて広い。 例えばコンピューターソフトウェアも一つの非常に重要な「コンテンツ」だ。これはMicrosoftが長期に渡り最重要視してゆくものでもある。 -->しかし、ほとんどの企業にとっては、情報や娯楽が重要な「コンテンツ」だ。そういう意味では、どんな小さな企業でも、コンテンツで事業を起こすことができると言える。インターネットがあれば、誰でもコンテンツを世界配信できる
インターネットの魅力の一つは、PCとモデムさえあれば、誰でも、どんなコンテンツでも、自分が創りだしたものを世に出せるというところだ。 ある意味、インターネットは写真コピー機のマルチメディア版といえるだろう。というのも、どれだけ受け手が多くても、低コストで素材を複製し配信できるからだ。 コンテンツ保有者が、基本的にコストゼロで情報を世界配信することも、インターネットがあれば、可能だ。極めて有利な条件なので、多くの企業がインターネットでのコンテンツプランを練っている。(ゆえに)コンテンツ産業は激しい競争にさらされる
例としては、テレビ局のNBCとMicrosoftは、インタラクティブニュース事業に共同で取り掛かるプランに最近合意したところだ。当社はNBCと共同で、ケーブルニュース網MSNBCを所有することになる。これはインターネットにおけるインタラクティブニュースサービスでもある。このジョイントベンチャーで編集権があるのは、引き続きNBCだ。 人気のあるコンテンツ、つまり(Microsoftが関わる)ソフトウェアやニュースだけではなく、ゲーム、娯楽、スポーツプログラム、電話帳に求人広告、さらには主要な分野専門のオンラインコミュニティなど、あらゆるカテゴリーにおいて、社会は激しい競争にさらされ、有り余るほどたくさんの成功者、そしてそれと同じくらいの失敗者が現れるだろう。紙のメディアで進むオンライン化の実例
今のところ、一般的に興味を持たれるような情報を配信する分野では、紙の雑誌がリーダーシップをとっているが、これがいずれ電子オンライン版で配信されるようになるのは、想像に難くない。紙の雑誌よりはるかに高いインタラクティブ性が必要
しかし、紙の雑誌でやっていたことをそのまま電子版に持ち込むだけでは、雑誌がオンラインで成功することはできないだろう。オンラインメディアの持つ欠点を凌駕するような情報の深さ、あるいはインタラクティブ性が、紙のメディアには欠けているからだ。 もし、受け手に対して、PCに向かってスクリーンで文章を読んでほしいのなら、深くかつ極めてリアルタイム性の高い情報を、誰もが好きなように検索して手に入れられるようにする必要がある。音声や動画も必要かもしれない。 そうした情報には、紙の雑誌でいう「投書欄」よりもはるか高いレベルで、読者が個人的に関わることのできるようなきっかけが必要になるだろう。
面倒な紙メディアからオンラインへ移行する科学雑誌
紙のメディアで興味を持たれるような情報を配信する同じような企業が、オンラインだとどれくらい成功するだろうか?多くの人は懐疑的だ。それどころか、紙の雑誌のいくつかは、すぐ近い将来にインターネットで存在が脅かされるだろうと目されている。 例えば、科学専門分野の情報流通では、インターネットで革命が起きている。 そもそも、紙の科学ジャーナル誌はだいたい高価である。流通規模が小さいからだ。主な市場は大学図書館で、情報配信の方法としては面倒だし、時間がかかるし、金がかかる。でもこれまでは、これしか方法がなかったのだ。 それが現在では、科学的な発見をインターネットで出版し始めた研究者がいる。こうした試みは、古色蒼然とした紙のジャーナル誌の未来を脅かすものだ。今後ネットで利益を生むのは、コンテンツである
時間が立つに連れ、インターネットにおける情報の広大さはとんでもないものになってゆき、抗いがたい力を持つことになる。こうした「ゴールドラッシュ」のような雰囲気は、今のところはほぼアメリカに限ったものだ。しかし私は、コミュニケーションコストが下がってコンテンツの大部分が各国語に翻訳されるにつれ、この雰囲気が世界中を席巻するものと考えている。コンテンツ産業が回り出すまではしばらくかかる
インターネットの繁栄のためには、コンテンツの提供で収入が得られるような環境が必要である。ずっと未来にはそうなるだろうが、まだしばらくは、コンテンツ配信者側は利益を得るために悪戦苦闘することになるだろう。 こうした企業はしばらくの間、広告や有料配信といったものを通じて、多くの失敗を経験することになるはずだ。現在も、また今後しばらくも、こうした仕組みはそう上手くは機能しないだろう。新しいメディアはすぐには利益を生まない
少なくとも現在は、インタラクティブコンテンツ配信が行われるケースのほとんどは、熱意からくる無償の労働によったものとか、電子世界でなく現実世界で販売される製品のプロモーションのおまけ、といったものにすぎない。こうした取り組みというのは、「長い時間を経てもいつか利益獲得につなげてやるぞ」という信念がある誰かによって成り立っているケースもしばしばあるものだ。 長い目で見れば、広告は見込みがある。 インタラクティブ広告には、より多くの情報を伝えなくても、最初に目につくメッセージで注意を引ければそれでよい、という長所がある。そのあとユーザーは、さらに多く知りたければ広告をクリックすればいいし、広告主側も、ユーザーがそういう行動をとっているかどうか計測だってできる。 ただ今日では、インターネット上の有料コンテンツ配信とか広告といったものが生みだす収益は、ほとんどゼロだ。全部ひっくるめても二千万から三千万ドルだろう。というのも、広告主はいつだって、新しいメディアには手を出さないものだからだ。インターネットは確かに新しいし、今までにないメディアだ。広告は有望だが、ネットが「重い」うちはユーザーに嫌われる
広告主が手を出さない理由のいくつかは、まあ正当なものだ。多くのインターネットユーザーは、広告を見ても喜んだりはしない。なぜなら、広告主の多くが大きな画像を使うために、ダイヤルアップ回線ではデータダウンロードに長い時間がかかるからだ。紙の広告だと、いくら大きなスペースを使っても、読者はぱっとめくってやり過ごせるが、ネットはそうはいかない。 インターネット接続がより早くなるにつれ、広告読み込みを待たなければいけない面倒さは徐々に減り、ついには消滅するだろう。しかし、それは数年のちのことになる。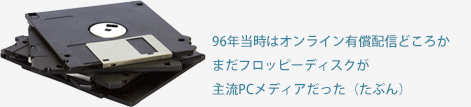
コンテンツ産業成功のカギは「少額課金」の実現
コンテンツ企業のいくつかは、有料配信の試みを行っている。ときには、無料コンテンツをエサにすることもある。手の込んだやり方だ。 しかし、電子コミュニティが有料配信になると、すぐサイト訪問者はがくんと減り、ひいては広告主にとってのサイトの価値もがくんと落ちるだろう。 このように、課金コンテンツの仕組みがまだうまくいっていない主な理由は、「少額課金」がまだ実現できていないからだ。電子取引にかかるコスト、そして面倒臭さが、高額な有料配信の相場よりも安く課金することを、実現不可能にしているのだ。インターネットは「コンテンツの市場」である
とはいえ1年以内には、コンテンツ提供者側が数円(1~数セント)で情報に料金をつけることができるメカニズムが実現するはずだ。 もし五円かかるコンテンツを訪問したいとして、そのために小切手を切ったり、メール同封の請求書をもらったりしたくはないはずだ。そういうときはおそらく、ほしいもののクリックだけが必要になっているのがよい。そして同時に、五円の請求が上がるのが集計ベースでわかるようにもなっているのだ。インターネットが「市場」になる瞬間
この技術が実現すると、サイト運営者は、多くの人を惹きつけるために、請求金額を少額にする、ということができるようになる。 こうして成功をおさめる人は、さらにインターネットを前進させるだろう。 そのときこそインターネットは、アイデアや経験や製品の市場、つまり、 「コンテンツの市場」となるのだ。 (C)2001 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use.
コンテンツイズキングをどう捉えるか?
コンテンツイズキングの風潮が、被リンク対策の困難さから始まったこともあってか、「コンテンツさえ充実してれば、SEO自体が必要ない」と早合点する人がいます。しかしそれは間違いで、”コンテンツイズキングを重視しても、これまでどおりSEOも必要”なのです。何故なら、SEOには”ウェブサイトをGoogleの閲覧しやすい形に整える”役割があるからです。
SEOが実施されていないサイトというのは、Googleからすると閲覧しづらい状態にあります。ですから、いくらコンテンツの質がよかったとしても、SEOが実施されていなければ、Googleから適正に評価されることは難しいのです。それは結果として、ユーザビリティを損ねることにもつながりかねません。
つまり、コンテンツイズキングはサイト作りの方向性を決めるものであって、SEOを否定するものではないということです。
ユーザー目線のSEOが重要
いかがでしたか?この記事では、”コンテンツイズキングでも、SEOは必要”だということを説明しました。ウェブマスターはサイトのコンテンツの質を向上させて、ユーザーの役に立つようにすることは大変重要ですが、Googleが適切にサイトを評価できるようにSEOを実施することも今までどおり大事なのです。
ウェブマスターは風潮に簡単に流されずに、真に”ユーザーにとって何が役立つことなのか”をしっかりと考えて行動することが必要になります。
- 高品質なサイト
関連SEO用語
- 無料で出来るSEO対策の方法を教えてください。
関連SEO情報
SEO Pack 費用・料金とご契約期間
必要な対策を必要な分だけ。SEO Packは余計なメニューが無いから高品質なSEO対策を低価格でご提供しています。
契約期間 |
3ヶ月 | 6ヶ月10%OFF |
|---|---|---|
お支払総額(税込) |
1ヶ月7,980円 (23,940円/3ヶ月総額) 定価23,940円/3ヶ月 |
1ヶ月7,182円 (43,092円/6ヶ月総額) 定価47,880円/6ヶ月 |
初期費用・追加費用 |
初期費用0円 0円(一切かかりません) |
|
サービス内容 |
・コンテンツ対策支援、内部対策支援 ・SEOツールの各種機能(順位計測、SEOノウハウの提供など)提供 ・被リンク10本設定 |
|
わずか数分でSEO順位上昇対策開始!
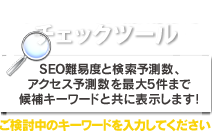
SEOツール無料トライアル
コンテンツ分析や内部SEO対策、競合分析ができるSEOツールが7日間体験可能!高機能なSEOツールを体験ください。