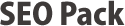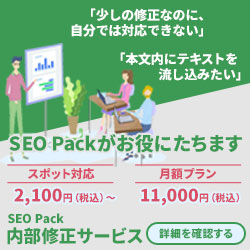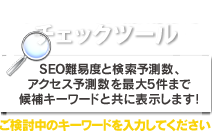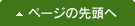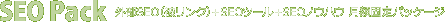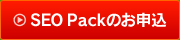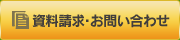[2016/08/18] (最終更新日 2022/05/13)
SEOに効く「パンくずリスト」対策ガイド
サイトのコンテンツ上部で目にする「パンくずリスト」。多くの場合、サイトトップから今開いているページまでの道筋を「>」などで表し階層構造をわかりやすく示しているものです。このパンくずリスト、実はSEO対策にも大きな効果があるのを、ご存じでしたでしょうか。
パンくずリストの価値はユーザビリティ向上だけではなくSEO対策にも効果的です。パンくずリストをうまく活用すれば、検索順位の上昇にも大きく役立てられます。
なぜパンくずリストがSEO対策に重要なのか、そしてどういった活用方法がSEO対策に最適なのか、本記事で説明します。

目次
パンくずリストの価値を再確認
「多くのページがカテゴリ毎に分類」「カテゴリは互いに上下関係を持っている」など、それなりの規模のサイトであれば、多くの場合、ページ上部にパンくずリストが設置されています。
こうしたカテゴリの上下構造を持つサイトでは、次のような大きなメリットが3つあります。
1. ユーザビリティ向上(サイト巡回しやすくなる)
検索ユーザーは、パンくずリストを確認しサイト構造を「ひと目で」理解できます。
例えば、あるキーワードで訪問した検索ユーザーが閲覧開始したページから他の関連するページも閲覧したい場合に、パンくずリストから、すぐにカテゴリトップに戻り、また別のカテゴリ内コンテンツを閲覧できます。
このようにユーザーが使いやすいサイトにする事で、サイト内閲覧ページ数を増やすことができるのです。
2. 内部SEO対策(検索順位が上がりやすくなる)
パンくずリストはSEO対策に効果的で最も大きいのが内部SEO効果です。
Google(Googleのクローラー)は、サイト内各ページを評価する際、サイト内の階層構造に従って、サイト内のリンクを辿り、リンクテキスト(アンカーテキスト)の内容を確認するといった手順を踏みます。
この手順に従い、クローラーは、サイト全体の構造を把握してGoogleデータベースに情報登録します。
したがってパンくずリストがあると、Googleクローラーは、最も適切かつスムーズにこの手順を踏み、サイトやページの価値を把握できるのです。
こうしたことから、正しく設置されたパンくずリストがある事により、クローラーが巡回しやすくなりサイト内のページが認知され、最終的にはサイトやページの順位を上がりやすくする効果が期待できます。
3. 検索結果でのクリック率対策になる
検索結果画面上にパンくずリストを表示させることができます。パンくずリストを表示させることで、ユーザーは適切なページを視覚的に把握する事が出来、検索結果上でのクリック率向上に期待できます。
正しい「パンくずリスト」設置方法
上記の3つのメリットを手に入れるためには、適切な方法でパンくずリストを設置する必要があります。その方法を次に説明します。
Googleがおすすめする構造化マークアップ
構造化データを正しく記述してGoogleにパンくずリストを知らせます。
構造化データの種類は「JSON-LD」形式と「microdata(マイクロデータ)」形式があり、Googleはどちらもサポートしていますが、2022年時点のGoogleのおすすめは「JSON-LD」のようです。
Google検索セントラルを確認すると「JSON-LD」形式も「microdata(マイクロデータ)」形式も、わかりやすく記述方法が紹介されています。
形式に従い、階層構造を記述した後に、「リッチリザルトテスト」で正しくマークアップされているかを確認してみましょう。エラーがあれば問題を修正する事で正しい記述になっているか確認できます。
ここでは、下記のようなパンくずリストを設置する場合を例に説明します。
「JSON-LD」による構造化マークアップでの記述
はじめに「JSON-LD」による構造化マークアップを用いると、下記のような記述となります。
- <script type="application/ld+json">
- {
- "@context": "https://schema.org",
- "@type": "BreadcrumbList",
- "itemListElement": [{
- "@type": "ListItem",
- "position": 1,
- "name": "SEO対策のSEO Pack",
- "item": "https://seopack.jp"
- },{
- "@type": "ListItem",
- "position": 2,
- "name": "高機能SEOツール「seodoor」",
- "item": "https://seopack.jp/seodoor/"
- }]
- }
- </script>
「microdata」による構造化マークアップでの記述
次に「microdata」による構造化マークアップを用いると、下記のような記述となります。
- <ol itemscope="" itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
- <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="http://schema.org/ListItem">
- <a itemprop="item" href="https://seopack.jp">
- <span itemprop="name">SEO対策のSEO Pack</span>
- </a>
- <meta itemprop="position" content="1"></li>
- >
- <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="http://schema.org/ListItem">
- <a itemprop="item" href="https://seopack.jp/seodoor/">
- <span itemprop="name">高機能SEOツール「seodoor」</span>
- </a>
- <meta itemprop="position" content="2"></li>
- </ol>
該当のページ内に構造化データによるパンくずリストを記述する事で、ページタイトルと一緒に、パンくずリストも適切に検索結果で表示されるようになります。
\無料診断の活用で課題を明確に/
外部リンク、内部状況、コンテンツ状況からSEO対策の課題が見えてくる無料調査です。
「対策ページの弱点は何か...」などお悩みをお持ちの方は、一度「SEOパーソナル診断」をご利用ください。
注意すべきポイント
パンくずリストを定義するには2つ以上のBreadcrumbListを定義
パンくずリストは少なくとも2階層以上の状態を表すものとなります。その為、構造化データでもBreadcrumbListというリスト内のすべての要素を保持するコンテナアイテムを2つ以上定義する必要があります。
素早い反映にはサーチコンソールの「URL検査」機能を使う
あなたのサイトのパンくずリストを構造化データによるマークアップに変更したからといって、そのままでは、すぐに検索結果に反映されるわけではありません。Googleのクローラーがページを確認し、データベースに情報を反映するまで待つ必要があるからです。
できるだけ早く反映させたい場合は、Google Search Console(グーグルサーチコンソール)の「URL検査」機能を使うことで、Googleのデータをよりスピーディに更新させることができます。
内部SEOだけで満足せず、SEO基礎をしっかり固める
もう一つ注意したいケースとして、こうした内部SEOをサイトに施工しただけでなんとなく満足してしまうケースがあります。
内部SEO対策により、サイトの順位は「上昇しやすく」なりますが、これだけでは順位は上がりません。外部SEO対策による被リンク獲得と、揃えて対策して初めて順位が上昇します。
そのため、SEO対策を行うサイトがある場合は、パンくずリスト整備を含む内部SEOと同時に、SEO Packによる外部SEO対策も必ず行うようにします。
そうすることで、徐々に順位が上がっていくのに加え、サイト価値の上昇により、その後のコンテンツ追加の際など、それぞれの新規ページも順位上昇しやすくなります。
おまけ
ちなみに名称の由来は、童話「ヘンゼルとグレーテル」の主人公が、森の中で帰りに迷わないようパンくずを落として進んだ、という話から来ています。英語でも breadcrumb(ブレッドクラム=パンくず)と呼びます。
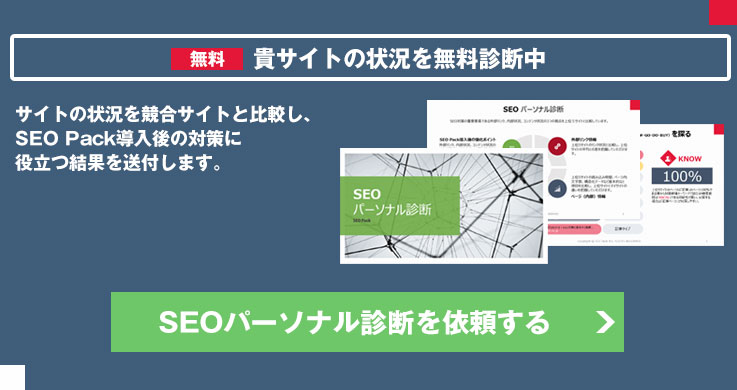
この記事が役に立ったらSNSで共有してください。