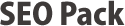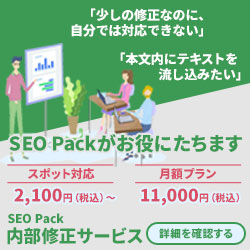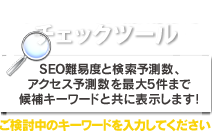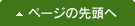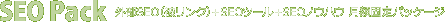「FAQ」カテゴリの記事一覧
[2016/06/14]
PC版とスマホ版が「全然違う」サイトは、Googleからチェックが入る
同じサイトのPC版とスマホ版(モバイル版)では、フロントエンドが違うだけで内容はだいたい同じなのが普通です。しかし、PCサイトとモバイルサイトの両バージョン間で内容まで大きく違うと、Googleからなんらかのチェックが入る、とGoogleが発言しています。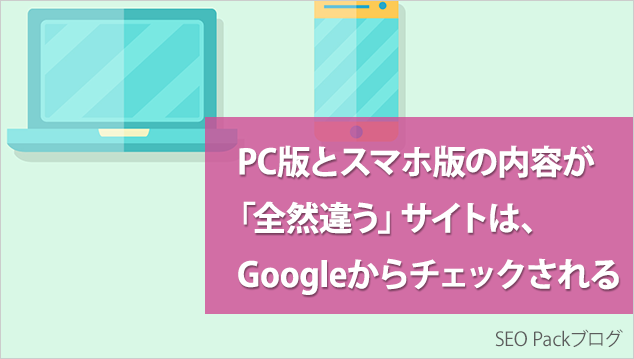
- PC版サイトとモバイル版サイトで内容が大きく異なる場合、Googleがチェックを行う可能性がある
- 基本的にはデスクトップ版の評価がモバイル版にも適用される
- 全く関係のない異なる話題を扱うと、手動ペナルティの対象になることもある
- 通常はPC版とモバイル版で内容を大きく変えるメリットはほとんどない
一番「○○」に詳しいページは?「Site:」コマンドで調査

- Googleはドメイン内で最も「キーワード」に詳しいページを評価する
- 同じ内容のページが複数あると、検索順位や内部リンクの効果が分散する
- 「Site:」コマンドでドメイン内の評価されているページを調査できる
- 希望のページが上位表示されない場合は、タイトルやコンテンツの見直しが必要
- TOPページにキーワードに関する情報を追加することで評価を上げることができる
- 目的に応じて、評価されているページの変更が本当に必要か検討することが重要
Googleなどの検索エンジンは、ページ内にどのような情報があるかというページの内容を評価するとともに、ドメイン内で一番「キーワード」に詳しいページはどれかを評価しています。
その為、ドメイン内で同じ内容(キーワード)について記載されたページが複数あると、次のような問題が発生します。
- ドメイン内で競合状態となるので、狙っているページが上位表示されない
- ドメイン内で、キーワードに関する内部リンクが分散されるため 内部リンクによるサイトパワーが付きにくい
ドメイン内で、同じ内容について記載されたページが複数ある事は悪いことではありませんが、重複ページと判断される懸念もあります。
したがって、上位表示させたいページとキーワードがあった場合、そのページとキーワードがドメイン内で最も評価されるようにGoogleの評価を上げる必要があります。
この記事の続きを読む…
正規化URLを調べるかんたんな方法(canonical動作チェック)
Webサイトのモバイル対応やAMPページ作成などで必要になってくるページの正規化。
「URL正規化」というのは、基準となる(=canonical)正規ページ(代表的なページ)を定め、同じコンテンツを持つ別のページ(=重複コンテンツ)にSEO評価が分散しないようにするために必要な処理ですが、正規化されたページがどのURLなのかを簡単に調べる方法を、Googleが明かしました。
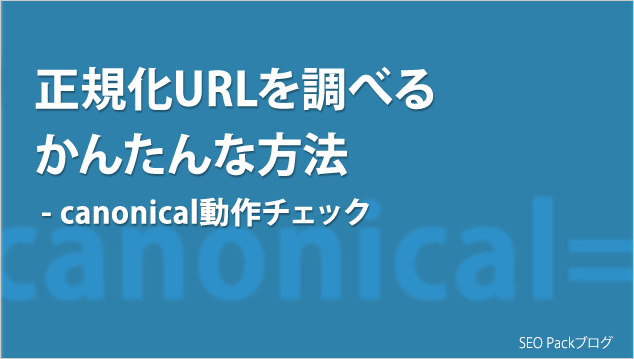
- URL正規化(canonical)の基本と必要性がわかる
- Googleで正規化URLを調べる方法(infoコマンド・サーチコンソール)を解説
- 301リダイレクトや.htaccessによるURL正規化の設定例を紹介
- 自己参照canonicalの意味と推奨理由を説明
- 正規化設定ミスによるSEO上のデメリットを解説
[2016/06/03]
Googleに「インデックスされない」ページとは?
あなたのサイトをGoogleの検索結果画面に載せてもらうには、まずGoogleがあなたのサイトを認識し、Googleのデータベースに登録してもらう必要があります。このデータベースを「Googleインデックス」、そこに登録されることを「Googleにインデックスされる」といいます。
新しいページを作ったり、既存ページを変更したりすると、ほとんどの場合は「しばらく」待っていれば勝手にGoogleがインデックスしてくれるはずです。しかし、そうならないケースもあるのです。
Google発言をもとに、ケース種別と解決策を説明します。

- Googleインデックスとは何か、その仕組み
- Googleにインデックスされない主な原因
- インデックスされない場合の確認方法
- 「検出 – インデックス未登録」「クロール済み-インデックス未登録」の意味
- インデックスされない場合の具体的な対策
- どうしてもインデックスされない場合の対応策