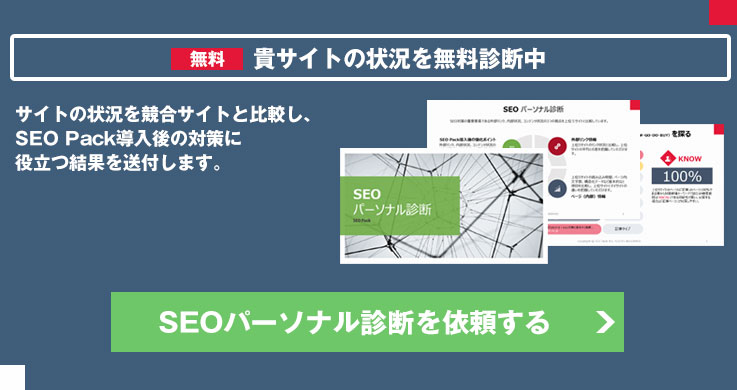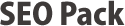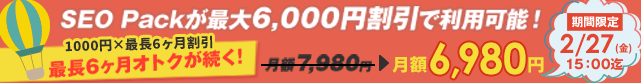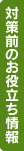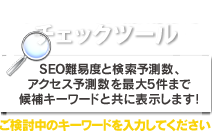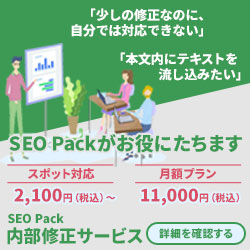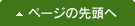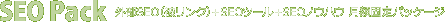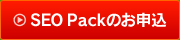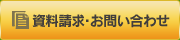アナリティクスで見る直帰率の平均値と考えられる改善点とは?
アナリティクスで直帰率を確認すると、意外と高くて何とか改善したい…と考えている方も多いかと思います。
今回は、その直帰率について平均値やページタイプと数字の関係など、具体的な改善点をまとめていきたいと思います。

直帰率とは?
直帰率とは、ユーザーがはじめて訪れたページ(ランディングページ)の次に遷移したページが他のサイトの場合や、戻るボタンを押した場合、あるいは、訪問したがウィンドウを閉じてしまった時の割合の事を直帰率といいます。
直帰のイメージは以下をご確認ください。

さて、直帰率は離脱率と混同しがちですが、
離脱率とは、個々のページのページビューの中で、最後のセッションだった場合の割合です。
サイトにアクセスしたユーザーはいつかサイトを離れます。離脱率は、どのページでサイトを離れたのか?そして、その割合は?という意味です。
サイト全体の離脱率が無いのは、このためです。

直帰率の目安
直帰率はどの程度を目安とすると良いのでしょうか。
これは、ページのタイプにもよります。
ブログ記事や1枚ペラページであるランディングページの場合、そのページに目的があるため、ユーザーがそのコンテンツだけで満足することによって、比較的、直帰率が高くなります。
反対に、モールやポータルのようなサイトだと商品や情報を探したり、条件を絞って検討するため、直帰率は低くなる傾向にあります。
これを踏まえて直帰率40%辺りを基準にページタイプを考慮して平均を想定してみると良いかもしれません。
例えば、管理しているサイトのトップページの直帰率が、60%だとしたら、改善の検討をしてみるべきでしょう。

\無料診断の活用で課題を明確に/
外部リンク、内部状況、コンテンツ状況からSEO対策の課題が見えてくる無料調査です。
「対策ページの弱点は何か...」などお悩みをお持ちの方は、一度「SEOパーソナル診断」をご利用ください。
ユーザーが直帰する理由
では、具体的にユーザーが直帰する理由を考えてみましょう。
ユーザーが直帰するには様々な理由が考えられます。
- 欲しい情報がない(メタタグが的確ではない)
- ページが見づらい
- アクセスしているデバイスにサイトが対応していない
- CTAなどの導線が不十分
まずは、直帰する理由は何なのか?考えてみましょう。
直帰率の具体的な改善案とは
ユーザーは何かしら、「したい・知りたい」などの意図があって検索します。
その検索結果の中から、自分の探している答えのありそうな魅力的なページタイトル、ディスクリプションを見つけてクリックします。
アクセスした結果、求めるものではない・わかりにくい、といったページだと戻ってしまうと予想できます。
これを防ぐために、次のような改善案が考えられます。
- タイトル・ディスクリプションを見直してみる(内容に合わせる)
- ページ内のコンテンツを改修する
- 魅力的なキャッチコピーを置いて読みたくさせる
- フォントサイズ・行間を読みやすく改善してみる
- モバイル対応してみる
- グローバルメニューを精査して改善する
ユーザーの求めるものに、応えられるページ作りをすると、自然と直帰率も下がります。
このように、直帰率を改善するには、マイサイトにアクセスしてくれた理由を考えて、ひとつずつ、改善してみることが大切です。
また、サイトへの集客経路によっても直帰率に違いがあるので、
こちらも調べておくことで直帰率が低い理由が見つかります。
下記の記事もぜひ参考にしてみてください。
\無料診断の活用で課題を明確に/
外部リンク、内部状況、コンテンツ状況からSEO対策の課題が見えてくる無料調査です。
「対策ページの弱点は何か...」などお悩みをお持ちの方は、一度「SEOパーソナル診断」をご利用ください。
直帰率はページの特徴や集客経路により改善の対応が様々
今回は、直帰率についてまとめましたが、ユーザーが直帰したとしても、滞在時間が長い場合は、直帰率が高くても問題ないという判断も考えられます。
直帰率の平均値はそのページの特徴にもよるということです。
SEO対策の効果を検証するためには、直帰率以外にも参考になる指標があるので、ページタイプなどを考慮した上で改善するようにしましょう。